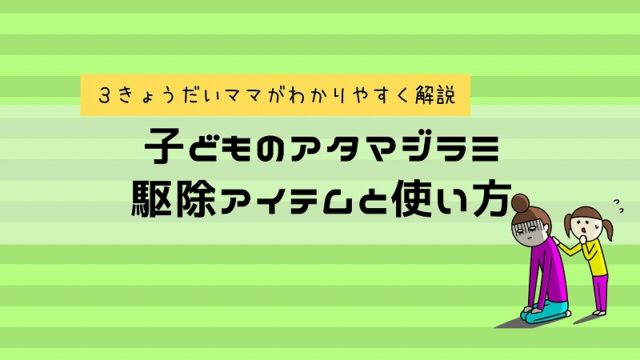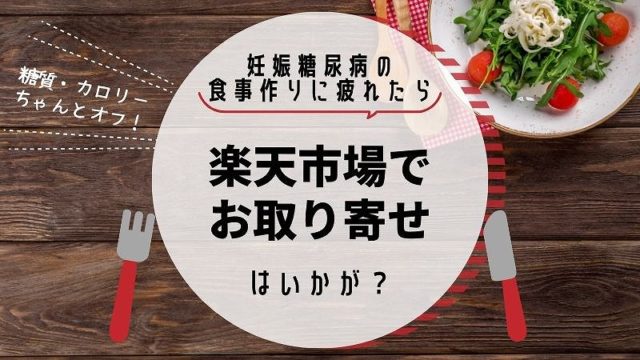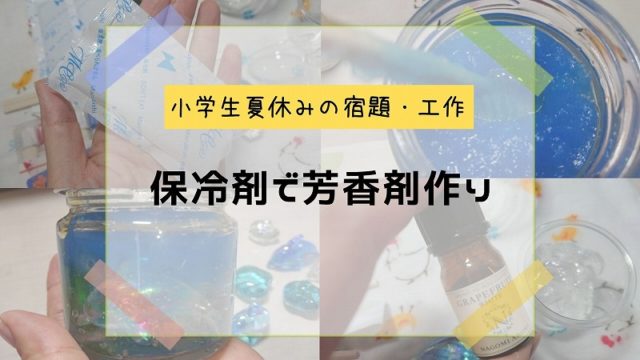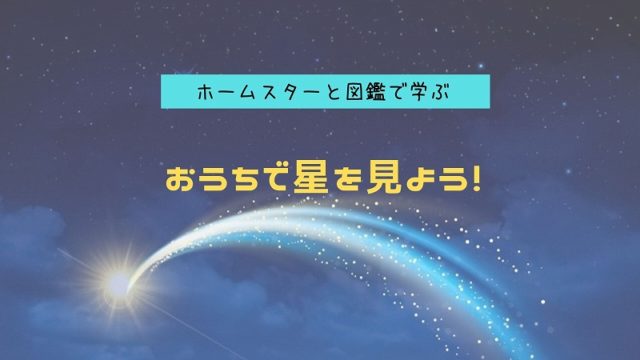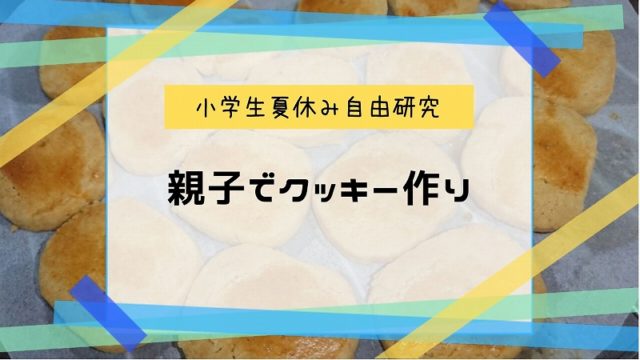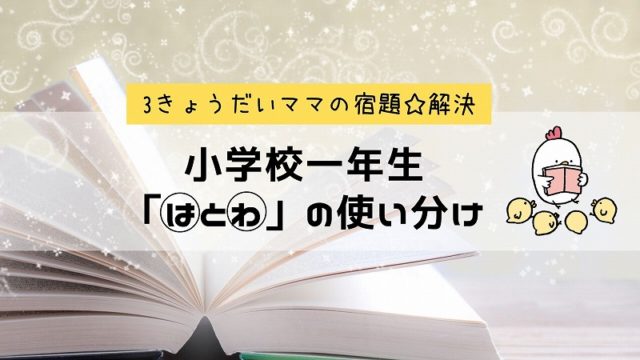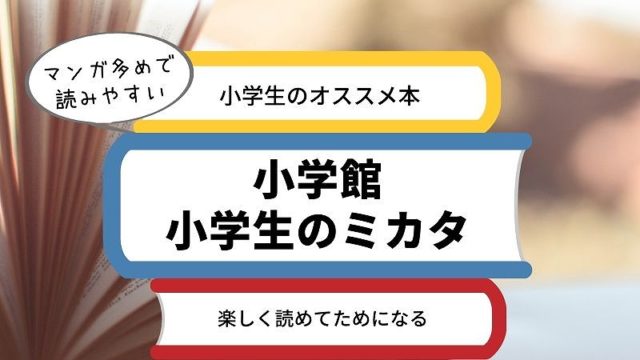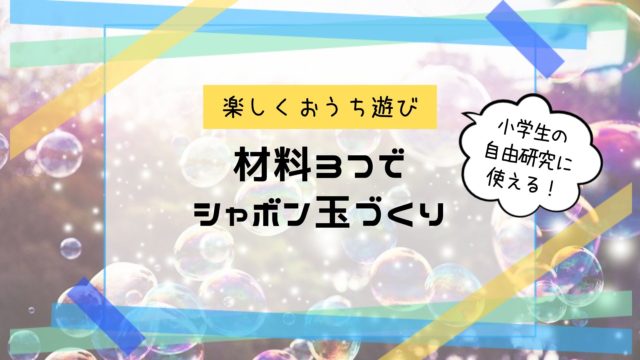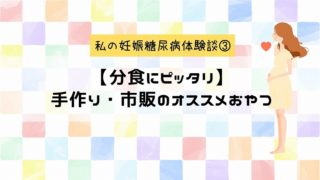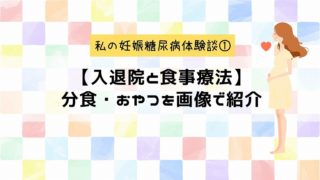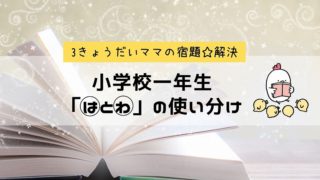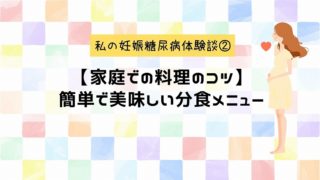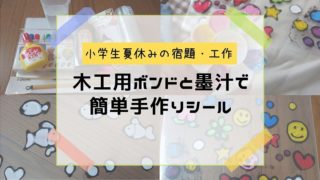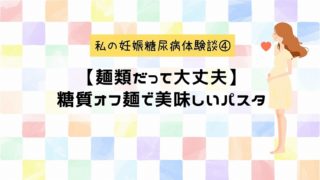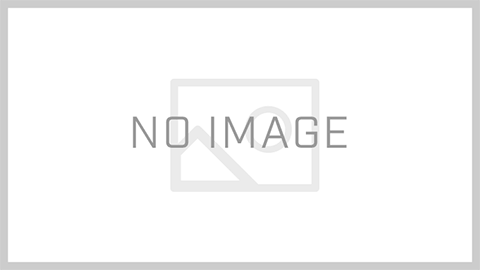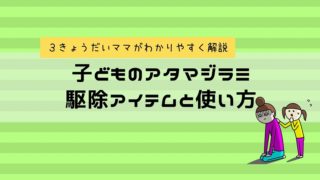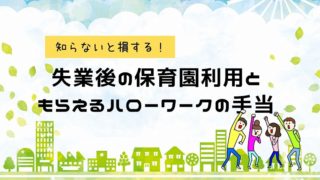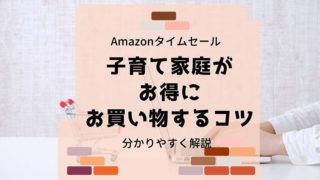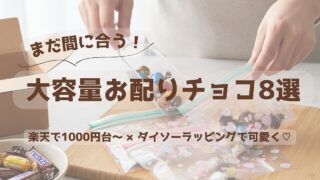【簡単】アサガオで作る工作作品と自由研究【小学生の夏休みにも】

小学生のお子さんがいる方、お子さんが学校から「アサガオ」を持ち帰ってきたご家庭の方向けに、アサガオで作る工作作品と自由研究を3点ご紹介します。(ご自宅でアサガオを育ててるご家庭も!)
- アサガオ染め紙のうちわ
- アサガオ染めのコットンマスク
- アサガオ押し花のハーバリウム
実は、小学一年生の子どもが学校から持ち帰ってきたアサガオとは別に、観察途中で元気に育っていたアサガオを間引いたものも1学期のうちに持ち帰っておりまして、わが家の夏の庭はアサガオ大豊作…
せっかくなので、夏の思い出作りもかねて工作・自由研究にしてしまおうと、子どもと一緒に作品作りに取り組むことに決めました。
30分ほどで出来るものから、事前準備も含めて1日(作業時間は全部で10分くらい)と行ったものもありますし、大量のアサガオの花を保存する方法もご紹介しますので、悩める夏の自由研究の参考になれば幸いです!
アサガオの花が咲いたらやっておくこと2つ

作品を作る前に、まずはアサガオの花の保存方法についてお話します。
何の作品を作るかにもよりますが、これから紹介する2つの保存方法でそこそこの量が確保できるので、ぜひやって欲しいです。
ただし、小学生が1人で行うには難しい工程もありますので、必ず保護者の方の管理下で作業をするようご注意ください。
1.冷凍アサガオ作り
「冷凍アサガオ」は、アサガオ染めや色水実験をやってみたい場合に役立つ保存方法のひとつです(花の原型をとどめる必要が無いものに限ります)。
方法はシンプルで、咲いたアサガオの花の部分を採取してビニール袋に入れ、冷凍庫で保存するだけ(ジップ付きの袋に入れておくとなお良いです)。
庫内で花がバラバラに崩れても、そもそも色水を作る時に花をガッツリ揉みこんでしまうから、花の原型をとどめる必要が無いのです。
この方法であれば、大量にストックしておくことが可能で兎に角簡単なんですね(枯れたり変色していなければ問題ないでしょう)。
布を染める際には濃い色水を作る必要があり、花の量も多めに用意しておいた方が良いので、この冷凍保存はぜひ活用してくださいね。
ちなみに…
食品の近くにアサガオを置いて大丈夫…?
と心配な方もいらっしゃるかもしれませんが、食品への臭いうつり等はありませんでした(1か月ほど入れてたけど全然大丈夫だった)。
2.押し花保存(アイロン法)
2つ目の保存方法はアイロンを使った押し花です。

押し花の仕上がりを美しくするために、なるべく開いてすぐ(開ききってしぼみ始めていない)のアサガオで作業をした方が良いので、アサガオの花が開いたらすぐに採取して作業に取り掛かりましょう。
取り組むお子さんが小学校低学年の場合は、主に大人の方が作業を行った方が安全ではありますが…お子さんとよく相談した上で、どの作業を任せるかを予め決めておくと安心ですね。
工程は3つ
- アサガオの花を採取する
- オーブンペーパーに挟む
- 低温アイロンで10~15分かけてじっくり乾燥させる
工程これだけで、花を採取する際に「ガク」や「葉・ツル」も採取しておいて、全部押し花にすることも可能です。
その際は、厚みのある部分が完全に乾燥するまでに時間がかかるので、アイロンを当てすぎて焦げていないかを時々確認しながら作業してくださいね。
また、乾燥し終わったアサガオの花は、透明感があり美しくはあるけど、とてもデリケートです。
オーブンペーパーから剥がす時が一番ちぎれやすいので、この部分は大人の方がやった方が良いかもしれません(大人がやっても失敗することはありますが…)。作品によっては、オーブンペーパーごとカットして使った方が良いかもしれませんね。
乾燥後すぐに作品を作らない時は湿気を帯びてしまうので、雑誌の間に挟むなどして湿気ないような場所で保管しておきましょう。
また、『ドライフラワー=永久保存品』ではありません。比較的長持ちはしますが、徐々に色味が変化したり、退色したりしますので、その点はご了承くださいね。
3.押し花づくり(レンチン法)
大人の方が見守りに徹して、お子さんに作業を任せるなら「レンチン押し花」が比較的安全に作業が行えるでしょう。

簡単ではあるのですが、加熱し過ぎるとボロボロに崩れてしまったり、焦げてしまったりするので注意が必要です。
工程は3つ
- 採取したアサガオをオーブンペーパーで挟む
- ①をダンボールで挟み輪ゴムで固定
- 600wのレンジで1分~2分加熱する(量や大きさ、湿度で異なる)
レンチンで作る場合は、ガクや葉ついたままでも、割と短時間で乾燥させることが可能なのがメリットで、火傷の危険も少ないです(レンジから取り出す時だけ要注意)。
ただ、アサガオの大きさによっては中心部分が完全に乾燥するまで加熱してしまうと、花びらの周辺がもろくなって崩れたり、焦げることもあります。
まずは1分程加熱して、オーブンペーパーの外側に汁がべったりついてるようなら、追加で30秒…10秒…と言った感じで、細かくチェックしながら加熱すると失敗が少ないでしょう。
ガクや茎も一緒に乾燥させる時は、乾燥具合がムラになりやすいので、マメにチェックしながら加熱時間を調整してくださいね。
こちらの押し花もすぐに使わない場合は、雑誌に挟む等して湿気が少ない場所で保管しておきましょう。
実は、園芸用シリカゲルを利用したドライフラワーにもチャレンジしたのですが、アサガオの花びらはかなり薄く、乾燥後にシリカゲルから取り出す際にバラバラに崩れてしまったため、シリカゲル作戦は断念しました。(崩れた花びらはハーバリウムやレジンの封入に使えます!)
シリカゲルを使用したい方は、アサガオの花を段ボールや厚紙に挟んでおく等といった『ひと手間』を加えた方が、失敗が少ないかもしれません。(←この方法は私は試していないため何とも言えませんが…)
保存したアサガオで作る3作品
冷凍保存・押し花保存を先に説明しましたが、わが家ではこの後3作品を子どもと作りましたので、その作品をご紹介しますね。
アサガオ染めの半紙でうちわ作り
うちわに貼り付ける作業は面倒ですが、小学校低学年の子でも作れて、盛り具合ではかなり「映える」作品が作れるので、親子でアイデアを出し合って素敵なうちわに仕上げてみてくださいね。
- 冷凍アサガオひとつかみ(花10個分くらい)
- 半紙数枚
- 無地のうちわ
- のり、飾り用の折り紙など
ポリ袋に冷凍アサガオと少量の水(50CCくらい?)を入れて、しっかりと色がでるまで揉み込むだけで、これで色水は完成なのです。
この後は、この色水で色々染めて作品を作ります。
染め紙は、色んな模様や柄が出来ると綺麗なので、折りたたんだ半紙の角や辺に色水をチョンチョンと付けてそっと開き、ドライヤーで数分乾かせば完成です(乾かした後でも開けますが厚みがあって乾くまでに少し時間がかかります)。
わが家のうちわづくりは、染めた半紙を折り紙サイズにカットしてアサガオ型に折ったものをうちわに貼り付けるという、非常に面倒な工程をとりましたが…
せっかくの染め柄や模様が見えなくなってしまったので、あえてそのまま貼るのもアリだったかな~と思います!(せっかく染めたんだし…)
半紙を先にうちわに貼っておいて、アサガオの汁でお絵描き…なんていうのも個性がでて良いですね!小さなお子さん・低学年のお子さんだと、こちらの方が取り組みやすいかもしれません。
アサガオ染めのマスク作り
先に紹介した「うちわづくり」で残ったアサガオの汁で、ガーゼマスクを染めてみましたが、くすみピンク(物は言い様ですね笑)の優しい色合いに出来上がりました。
ガーゼマスクを作った当時は、新型コロナでマスクの供給が極端に少なかったこともあるのですが、現在はガーゼマスクを使う人は少ないかな(汗)
布製コースターやガーゼハンカチの方が使用しやすいかもしれませんね!
アサガオの押し花でハーバリウム作り
ちぎれてしまった朝顔の花や、残りの茎、葉なども利用して小4の娘がハーバリウムを作っていました。
容器は透明の乳酸菌飲料(R-1など)が扱いやすいです。ハーバリウム液はセリアで購入しましたが、ベビーオイルでも代用可能です。
アサガオの色素はポリフェノール
少しだけ余談ですが…アサガオの色素はポリフェノールで生成されています。
マスク染めの際に少量の酢を加えると鮮やかな赤に色が変わることを利用して、色水実験をすると「自由研究」にもなりますよね。
- 何色のアサガオを使ったのか
- 出来上がった汁の色
- 何を加えると色が変わったのか(変わらなかったのか)
こういった点を観察して、スケッチブックや模造紙にまとめると伝わる内容になるのではないでしょうか。(絵を描いても、写真を貼るのも分かりやすくていいですね)
ちなみに、色変を観察する際は、「酸性・アルカリ性の液体」を用意する必要があるのですが、酸性は一番身近な「酢」がありますが、匂いがに気になる方は、クエン酸やレモン汁で代用すると良いでしょう。(クエン酸を常備してる家庭は少ないか…)
それでは、アルカリ性はどうしよう…?
と迷った時は「セスキ洗剤」が良いかもしれません。(100均にも売ってます)
セスキは「重曹と炭酸ナトリウム」で構成されたアルカリ洗剤で、界面活性剤を含まないことから環境に優しい洗剤として注目されています。
ただし、口や目に入らないよう安全面に配慮する必要はありますので、色水実験の際は必ず大人の方の管理下で行いましょう。
身近な素材で楽しく作品作りを!

アサガオを使った作品作りと自由研究をご紹介しました。
今は、自由研究キットも色々なものが売られていて、逆にどれを選ぶかが難しかったりしませんか?
その点、身近な素材を使えば興味も沸きやすいですし、何より「低コストで入手が簡単」なのが、メリットだと私は思っています。
大人が頑張りすぎると「誰のための宿題か~」ってなりがちなので、アイデア出しと危険な工程に手を貸したら後はそっと見守るのも大事なのではないでしょうか。(難しいけど)
それでは、楽しい製作時間をお過ごしくださいね!